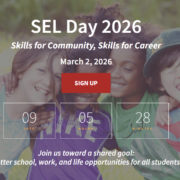映画「小学校~それは小さな社会~」を鑑賞して

昨年末、話題のドキュメンタリー映画「小学校〜それは小さな社会」鑑賞した。
自身が予想していた内容とは大きく異なり、琴線に触れた鑑賞の時間だった。久しく映画を見て泣いた記憶はないのだが、単純に感動した、とかそういう類の涙ではなかったようにも思う。この映画の特筆すべき点は、特別な理想の新しい学校でもなく、自由教育を推進しているわけでもなく、どこにでもある普通の公立小学校の日常を描いてる、ということ。

教員たちの葛藤、感情の揺れ動きがリアルで、最初は違和感ある言動の先生も、本音の部分が垣間見れる瞬間に人間的でホッとしたり、感情のふり幅が実に大きい映画だった。ありのままのオールロケを許可した世田谷区教育委員会、教員、地域、保護者の方々に敬意を表したい。
・コロナ禍で翻弄された2021年から1年間を撮影
・子どもたちと教員たちの日々の暮らしを描いている
・予見できないコロナ禍での一斉休校、緊急事態宣言発出で林間学校中止等、教員の奮闘ぶりや、翻弄される子どもたちの苦悩が赤裸々に描かれている
・一つの考えに誘導しがちなナレーションが全編を通してない
鑑賞後の受け取り方は様々で、既にSNSでも賛否両論が巻き起こっている。「違和感だらけ」「旧態依然とした指導法にゾッとした」などのコメント等が散見される。また鑑賞後のオンライン対話会等も方々で開催されているようだ。
映画の反対意見の多くの声として、学校の教育システムや教員たちからの指導に関する疑問が多いようだ。無論、日本の教育には多くの課題が山積していることは確かだ。ただ初めから学校批判、教師批判を見ると、私自身とてつもない違和感を覚えてしまうのだ。そして人は、なぜ頭ごなしに否定、批判、非難してしまうのだろうか、という問いも生まれている。
果たしてそこにはいったい、どのような感情が渦巻いているのだろうか、とも。
監督からのメッセージ
本作品を撮影した、山崎エマ監督のインタビュー記事で下記のコメントが目に留まった
「今は多様性や個人を重んじるがあまり「集団生活」や「団体行動」という言葉を使うだけで、ニュートラルではなくなっている感じがします。もちろん、一歩間違えれば同調圧力にもなりますし、集団にハマりにくい人たちが生きづらさを感じていることもわかります。ただ、悪いところは良いところと切り分けて課題として向き合うべきで、日本式の教育のすべてを否定してしまうと、何か大切なことも見逃してしまうのではないかとも思います。人間はいろんな人がいるコミュニティの中で、自分の居場所や役割、生きがいを見つけて暮らしていく社会的生物。日本の小学校はそうしたコミュニティで生きていくための練習の場なんです。今の日本社会に当たり前にある、日本人が気づいていない良いところに気づいて自信を持ってほしい」
違和感からの対話で大切にしたいこと
「すべてを否定しまうと、何か大切なことも見逃してしまうのではないか」
山崎監督のこの言葉に私はフックがかかっている。
沢山の課題はありつつも、この映画を通して、少なくとも聖人君子に仕立て上げられがちな、教員たちも一人の人間なのだ、と捉えることが出来るのではなかろうか。懸命にもがきながらも前へ進もうとする姿にいつしか映画に没入していたのかもしれない。これからの日本の教育で大切にしていくことは何か、また変わっていくべきかの議論をする上でのたたき台にもなる映画ではないか、と感じている。
日常生きていく中で、沢山の違和感を覚えることは誰しもあるはずだ。そんな違和感からの対話で大切にしたいこと、これを今月のTea Timeのテーマとした。ぜひご参加いただきたい。

生きる力をつくる・はぐくむをコンセプトとした
Art-Lovingというアートカンパニーで、演劇創作と演劇共育を中心とした教育事業に勤しむ。
舞台演出家・演劇共育実践家・ラジオパーソナリティ(FM軽井沢)として活動中。