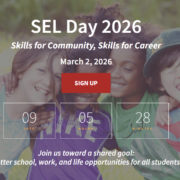不完全で大丈夫

先日、本屋でふと目に入って、なんとなく購入して読んでいる本(不完全主義 限りある人生を上手に過ごす方法)があります。案外面白かったり新たな気付きもあったので、8割ほど読み進めたところですがその時点での自分なりの解釈や特に印象に残った点、気付きなどを紹介したいと思います。
自分の中の有限性を受け止める。全てを完璧にというのは無理
様々なタスクに追われて大変…とにかく全て完璧にこなさなければ…と思う人は世の中に多いかと思います。私もそういった思考になることはあります。そして、完璧にこなせない、失敗すると落ち込んで自己嫌悪に・・・特に完璧主義な方はこういった負の連鎖になってしまうことがあるのではないでしょうか。
ですが、人間、誰しも無限に何かをこなせるわけではなくて、時間や能力にも限界があります。なんとなくというか、無意識に「何とかすれば全てをこなせる」と思ったりすることがあると思いますが、それは大きな勘違いで人間は皆それぞれ有限であるということ。「自分の有限性をまずは受け入れる」ことで少し楽になれる気がします。
自分の有限性を受け入れると、全てを完璧にこなすのではなくて、この有限性の中でどんな選択をするか。選択肢の中でどこに注力するか。そして、選択したことが少しでも達成できたらそれでOK。そうやって自分で自分を認めてあげたらいいと思います。特に、完璧主義的な思考な人や、ストイックな人・・・ストイックなこと自体を否定するわけではないし、むしろ時と場合によってはストイックになった方がいい時もあるかと思います。ですが、得てして、そういう思考の時には「自分自身に厳しい言葉がけをする」つまり、「他者には掛けない言葉がけを自分自身にする」傾向があると思います。
例えば、テストで100点目指していたけど、80点だったとき。自分自身には「もっといけただろ!詰めが甘いんだよ」といった声がけをするかもしれませんが、これを敢えて同じ状況の他者には掛けないと思います。きっと「そうは言っても。80点は凄いよ。頑張ったじゃん!むしろ悔しさが次のエネルギーになるね」などと前向きな言葉をかけるのではないでしょうか。
自分の有限性を受け入れたうえで、自分自身には「他者にかけるような声がけ」「他者から言われたい声がけ」とも言えるでしょうか。そうすることで、もっと心地よく生きていけるのでないかと感じました。
「山を越えればまた山がある」そもそも、人生はそういうもの
なんで、こんなに問題ばかり起きるんだ・・・一難去ってまた一難・・・いつか平穏が訪れるのか・・・色々なことが重なったりしてこういった想いになることもよくあります。そして、こういったことを嘆いている時、実は無意識に我々は「いつか人生は何の問題もない、平穏な時が訪れる」という前提にたっています。ですが、本当にその前提は合っているのでしょうか。その時を待っている間に時だけが過ぎ去っていきそうです。
仏教の世界でも「人生には苦しみが伴うもの」としていますが、そもそも人生とは問題が起きて解決したらまた何かしら問題が起きるものです。まさに「山を越えればまた山がある」です。皆さんが、今までの人生を振り返ってもそうだったのではないでしょうか。もちろん、その山はとてつもなく大きな山からちょっとした丘など様々かもしれません。なので、これもまずは前提を捉え直して、「人生に問題はつきもの」と受け入れることで少し楽になれる気がします。そして、その問題も後から振り返ってみるとどうでしょうか。それは1つの経験となったり、自分自身を創り上げる1つの叡智となったり、はたまた1つの笑い話になったり・・・
人生にはコントロールできないことが多いし、不確実なことも多いから問題だって起きる。でも、だからこそ、思いもよらないことが起きるし、それが1つの魅力かもしれません。私自身も、まさか今のような仕事をしているとは思いもよらなかったことの1つです。(良い意味で)
過去でもなく、未来でもなく、「今」に意識を向ける
この有限性の中で、どこに注力するか。それを過去を悔んだりすることでもなく、未来を願うことでもなく、「今」ここに集中してできることすることだと改めて感じました。同じことは、釈迦の言葉でも聞いたことがあって何か繋がりを感じました。「今」を楽しむ。「今」を味わう。「今」したいことを少しでいいからする。「今」できることをする。
自分自身も若干不安症で未来のことを気にするあまり「今」に集中できていないといったことがあります。そうなった自分を客観的に認識した上で、「今」に意識をもってくる。「今だけが実在している本当の時間で、その瞬間こそが自分の人生」といったことを意識してけたら、今まで以上に良い意味で楽に上手に過ごせそうだなと感じました。

金融機関での勤務や9年間の公立中学校教師生活を経て
現在は放課後等デイサービスで学習指導やSSTを行う
自分自身も、子どもたちも「自分らしく生きて幸せに」というモットーのもと
教育に携わっています