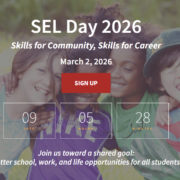セルフサイエンスは、ピンチの時の道しるべ

今年も残すところ、1ヶ月半。
毎年、時の速さの実感を感じますが、今年は尚さら感じました。
きっと、この1年予期せぬ出来事が起こったり、何かとバタバタしていたからかもしれません。
でも、セルフサイエンスの学びがあったからこそ、最善の選択ができたことも事実です。
日常生活で起きた大小の出来事を通して振り返りつつ、発見と気づきを書き留めておきたいと思います。
ピンチ!母が手術しなければならないかも
それは、ある日突然知らされました。
『あのね…手術をしなければならないかもしれない…』と言う母からの電話。
この言葉に、何をどのように紐解いて良いのか、一旦私の思考が停止しました。
色々な感情が沸き起こる中、感情にハイジャックされないように、深呼吸しながら整え、
思考を働かせて質問すると、ようやく全容が見えてきました。
約、2年に渡って、舌にできた出来物の経過観察をしていたのですが、一向に改善しない為、
組織の検査をしたところ、一刻も早く手術が必要であるとなったのです。
この急展開に、母をはじめ、家族ともにかなり動揺しました。
一刻も早い手術をと迫られる医師、決断できない母…。それを見ている家族…。
一人ひとり、様々な感情を抱いていたと思います。
本人は勿論のこと、側にいる父は、また違った立場で抱く感情があり、少し距離がある私や妹は、
客観視しながら抱ける感情が存在し、一つの出来事を通して抱く感情は、自分の置かれているポジションにおいても
結構な違いがあることに気付かされました。
そうした中、母は《決断を早まってはいけない》と何度も言っていました。
それは、自分の感情にフォーカスした時に、ザワザワした感覚があり、心地よくなかったからだそうです。
医師からの《一刻も早く…》の言葉に、焦りと大きな不安を抱きながらも、違和感を感じることができたのは、
母もEQの学びを継続しているからだと思いました。
この《心地良くない》という違和感に基づき、手術をしない選択をし、更に思い切って、
組織の一部を切り取り、生検するという選択をしました。
その結果、手術の必要はなく、患部も完全回復に向かっています。
あの時、自分の心地良くない感覚に気づき、抱いた違和感を大切にすることにより、大丈夫だという自分への励ましが加わり、少々リスクを伴う組織を切るという思い切りに繋がることができたのでした。
自分の内側に沸き起こる感情からメッセージを受け取り、メッセージを良く味わい、思考と繋げて行動する…
この一連のプロセスは、ピンチの時にこそ活きるスキルであると実感しました!
ピンチ!娘の学校からの電話
先日、仕事で遠くまで外出している時に、娘の学校から電話がありました。
学校からの電話に、ドキッ!とするのは私だけでしょうか…。(何だかよく分からない、何かしでかしたか…という思い)内容は、娘が少し元気がないので、お迎えに来て欲しいというもの。
娘はダウン症のため、学校の送迎を私が行っているのですが、娘が学校に行く時は、すぐに対応できるように、
仕事をセーブしていました。
しかし、この日はどうしても調整ができず…。
この時に抱く感情、《迷惑をかけて申し訳ない》この一択に限っていました。
ことの説明をすると、先生から、「大丈夫です。こちらで様子を見ていますね」と温かいお言葉をいただき、
この言葉で、安堵し、仕事を早めに切り上げ、学校に向かいました。
クラスのお友達が一緒にいてくれたことにより、1日を乗り切ることができたようです。
この出来事を通し、娘が産まれてから、《この子を守らなければならない》という思いが強く、
この強さが意識から無意識の領域でも働いてしまっていることに気付かされました。
娘も中学生。娘にも年齢とともに広がっていく世界があり、《私が守らなければ》の思いが、時にその世界に制限を
かけてしまっていたのです。
また、《みんなに迷惑をかけて申し訳ない》という思い。
以前、日常会話でよく使う「すみません」の意味についてクラスで取り扱った内容を思い返してみました。
日常会話でよく使う「すみません」の意味
意味①『ごめんなさい(謝罪)』
意味② 『ありがとうございます(感謝)』
特に②として、日本人は、相手が自分のために何かをしてくれた時、《手間をかけさせてしまった》とか
《時間をとらせてしまった》などといろいろ考えてしまいます。(その為、感謝には【謝】の文字が入る)
本当は「ありがとうございます」の気持ちを表現したいのですが、感謝の気持ちのほかに、
上記のような理由で「悪かった』という気持ちも込めて、「すみません」を感謝の言葉として、よく使うようです。
日本語としての奥深さはありますが、娘を迎えに行って1番はじめに抱いた感情、それは、《ありがとう》という
感謝でした。
申し訳なかったという感情も存在しましたが、私に与えてくれた《ありがとう》という嬉しい感情をダイレクトに
受け取り、そのままを言葉にできたことが嬉しかったです。
自分に向けて発信してくれた感情に忖度しない!これも大切なことかなと思いました。
ピンチ!息子が大親友と大喧嘩
息子は、高校2年生。
中学生から本格的にボウリングを始め、毎週末は、全国各地で行われる大会に出ています。
この喧嘩の発端は、仲間と一緒に練習する中で起こりました。
多感な時期の高校男児…練習中にも様々な感情がうごめいています。次の大会に向けて調整していくので、
大事な大会であるほど、ピリピリ感がリアルに感じられるようです。
自分のイメージに当てはまっていかない時の感情や行動が山積し、お互いに口を効かず、距離を置く日々が続いました。次の大会では、チームを組むことになっていたため、コーチを始め、周囲のお友達も心配していたようです。
見るに見兼ねた友達が、《いつまでも、冗談を言って笑っていられる関係でいたいから、問題を感じたら話合ってみよう》と息子にLineを送ってくれたそうです。
この内容を見た息子は、話すことを決意し、練習後に話をするになりました。
ここは大親友の醍醐味、思っていたことを全てここに出そうとなり、口喧嘩に発展。
しかし…お互いに尊敬している部分も言葉にでき、泣いてしまったようです。
良い関係とは、問題に直面した時に、どのように対処し、お互いに心に留め合うことができるか…。
きっかけ作りに貢献してくれた、友達の存在に感謝です。彼は、諦めずに何度も言葉をかけてくれたそうです。
友達の状況に気づき、何とかしてあげたいという思い、この思いを持ち続け、諦めずに行動に起こしたそのものが
セルフサイエンスだと思いました。友達からのアプローチにより、息子は何をしたら良いかの選択ができ、大親友とも、更に強い絆で結ばれたことと思います。
その後の大会で行われたチーム戦では、惜しくも準優勝!2人ともやり切った感満載の表情でした!
セルフサイエンスは、日常生活の大小の出来事に対して、道しるべになってくれるものです。
生活に密着させて活かしていくことの大切さをこの度も考えさせられました。
その為に、学びの継続が必要なのです♪

児童養護施設の職員を経て、子どもの関わりにEQの領域が必須であることを実感。
現在、学童保育にEQプログラムを導入し、子ども達とワクワク感を体感中です。
すべての人が、 心から【だいじょうぶ】だと思える世界をつくりたいと願い、活動中です。